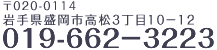第14回岩手甲状腺眼症研究会抄録
1.特別講演Ⅰ
甲状腺眼症に対する新規薬剤テッペーザの治療経験と地域医療連携について
小笠原眼科クリニック
副院長 小笠原 聡 先生
甲状腺眼症(Thyroid eye disease: TED)は、視機能障害や外見上の変化により患者の生活の質を大きく低下させる疾患であり、内科的・外科的治療を含めた多角的アプローチが必要とされる。従来はステロイドパルス療法や放射線治療などが中心であったが、効果や副作用に課題が残っていた。
2024年11月に本邦で承認されたテプロツムマブ(テッペーザ®)は、IGF-1Rを標的とする初の分子標的薬として注目され、新たな治療選択肢を提供している。筆者は導入直後から活動期TED症例に投与を開始し、眼球突出や複視の改善を確認した。副作用として聴力の変化、血糖値上昇、下痢などが一部にみられたが、いずれも重篤には至らず、適切に対応することで治療継続が可能であった。
またTED治療全般を考えると、地域医療連携の重要性は非常に大きい。診断の早期化、活動性評価、副作用モニタリングに至るまで、開業医、基幹病院、大学病院がそれぞれの役割を担い、患者を切れ目なく支える体制が求められる。特に眼科と内分泌代謝内科(甲状腺科)の連携は不可欠であり、地域における情報共有と協働は治療成績の向上につながる。
本講演では、実際の症例も交えながらテプロツムマブの使用経験を報告するとともに、TED治療全般における地域医療連携の意義を改めて考察する。新規薬剤の登場を契機に、患者中心の包括的な診療体制をいかに構築していくかを議論したい。
2.特別講演Ⅱ
甲状腺眼症の発症を抑える内科治療のポイント
新古賀病院 糖尿病・甲状腺・内分泌センター顧問
久留米大学名誉教授 廣松 雄治 先生
甲状腺眼症は、自己免疫性甲状腺疾患に伴う眼窩組織の自己免疫性炎症性疾患で、多彩な症状を呈し、重症例ではQOLの低下をきたす。2011年にバセドウ病悪性眼球突出症の診断基準と治療指針が公開され、内科医と眼科医の連携、MRIによる病勢把握、眼症の重症度や活動性に応じた適切な治療法の選択が推奨されてきた。
2024年11月に発売されたTeprotumumab(Tep;テッぺーザⓇ)は、ヒト型抗インスリン様成長因子-1受容体(IGF-1R)モノクローナル抗体であり、IGF-1Rの下流のシグナル伝達を阻害し、線維芽細胞の活性化や増殖、ヒアルロン酸産生、脂肪細胞の分化・増生、炎症性サイトカインの産生や外眼筋腫大を抑制する。眼球突出に著効し、市販後は活動性甲状腺眼症の治療の第一選択として、中等症~重症の活動性甲状腺眼症診療にパラダイムシフトをもたらしている。
本講演では、わが国での臨床試験や市販後の臨床知見を中心に、Tepの有効性と忍容性について紹介し、甲状腺眼症の診断、発症予防と治療のポイントについて概説する。
【コントロール可能な増悪因子】甲状腺機能亢進症、TRAb高値、TSAb高値、甲状腺機能低下症(甲状腺腫術後やRI治療後)、免疫チェックポイント阻害薬の投与
【早期診断に有用な検査】CAS,QOL,MRIによる評価
【早期介入に有用な治療法】甲状腺機能の正常化、トリアムシノロンやボツリヌス毒素の局所投与、ステロイドパルス療法、放射線照射療法、Tep治療
【わが国でのTepの臨床試験】投与24週後の評価で、>2mmの眼球突出の改善率89%、CAS 0~1点への改善率59%、複視の消失率50%と良好。副作用として高血糖(22%)と聴覚障害(15%)がみられる。
【Tepの甲状腺眼症治療におけるポジッショニング】中等症~重症の活動性甲状腺眼症、特に顕著な眼球突出や複視のある患者、ステロイド難治性の患者には第1選択薬と思われる。使用にあたっては治療前および投与中、8回投与終了後の検査が推奨される。